グループホームという言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。
厳密にいうとグループホームは認知症高齢者向けのグループホームと障がい者向けのグループホームの2つに分けることができます。
ご存知の方も多いと思いますが、障害者総合支援法により障がい者向けのグループホームではサービス管理責任者(サビ管)を必ず配置しなければなりません。
そこで今回は障がい者グループホームでサビ管として働くメリット・デメリットについて解説していきます。

2つのグループホームの違いとは
先ほども説明した通りグループホームは認知症高齢者グループホームと障がい者グループホームの2つに分けることができます。
それぞれの特徴について見ていきましょう。
認知症高齢者向けグループホーム
認知症高齢者グループホームは認知症高齢者支援の担い手として誕生しました。
現在は多機能化が進み、デイサービス・ショートデイサービスなど利用者のニーズに合わせて様々な形で施設が運営されています。
施設運営や入居者に関する条件
・5〜9人の少人数で構成する。
・専門スタッフの支援のもと、家庭的な環境で生活をする。
・日中は利用者3人に対して1人介護従業員をつける。
・転職時は給与や福利厚生だけでなく、人間関係や業務量、キャリアアップの機会も考慮し、実務経験の積み重ねや研修・資格取得が収入向上に効果的。
・サビ管を常勤させる
・医師から認知症の診断を受けている。
・要支援2以上または要介護1以上の認定を受けている。
・ある程度自分の身の回りのことができる。
・年齢が65歳以上。
認知症グループホームの目的は、認知症の進行を抑え、機能維持を図ることです。
家庭的な雰囲気の中で、入居者の能力を最大限に活かし、個人の尊厳を保ちながら安定した生活を送ることができるように支援しなければなりません。
また、認知症グループホームは地域密着型サービスの一つであり、住み慣れた地域で暮らし続けられることも特徴の1つです。
障がい者向けグループホーム

障がい者グループホームは障がいのある人が支援を受けながら地域社会で生活するために設立されました。
まず障がい者向けグループホームは身体障がい者の場合、65歳までしか利用することができません。(※精神障がい者・知的障がい者は65歳を過ぎても利用可能)
どの型であっても障がい区分に関わらず利用することはできます。
具体的には、一人での生活に不安があり一定の支援を受けたい方や重度の障がいがあり支援を受けながら生活したい人などが利用します。
サービス内容としては夜間における日常生活の援助をするものになっています。
具体的には日常生活・社会生活上の相談及び助言や就労先やその他の関係機関との連絡などを行います。
障がい者向けグループホームは3つの型に分けることができ、型によって支援方法や手段が異なります。
介護サービス包括型
介護サービス包括型は夜間に介護支援もあわせて行う施設です。
事業所数・利用者数ともに一番多く、障がい者グループホームのスタンダードな形と言えます。
事業所数:7,718
利用者数:114,554
日中サービス支援型
日中サービス支援型は夜間だけでなく24時間介護を含めた支援を行う施設です。
重度の障がいがある方や高齢者の方が多く利用しています。
事業所数:182
利用者数:2,344
外部サービス利用型
外部サービス利用型は主に日常生活のお手伝いを行う施設です。
入浴や食事、排せつなどの介護にあたるものは外部の事業所に委託する形になります。
事業所数:1,321
利用者数:15,551
【参考:厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670104.pdf】
グループホームのサービス管理責任者の仕事内容

サビ管の仕事内容は多岐に渡ります。
様々な業務がある中でグループホーム特有の仕事内容はいくつかあり、個別支援計画の作成と利用者の管理など多岐に渡ります。
・利用者の希望やニーズを聴取し、最適な支援計画を立案
・定期的なアセスメントとモニタリングの実施
グループホームのサビ管は、他の施設と比べて直接支援に関わる機会が多く、利用者との密接な関係を築きながら、その生活の質を向上させる重要な役割を担っています。
また、常勤でなくても良い場合があり、短時間勤務の機会もあります。
利用者に対するサービス内容
日常生活支援 :食事の準備、掃除、洗濯、入浴、排せつ介助などの日常生活に関する援助
機能訓練 :歩行訓練、認知機能訓練などの機能維持・向上のための訓練
レクリエーション活動:カラオケ、ゲーム、創作活動などのアクティビティ
外出支援 :買い物、通院、散歩などの外出に関する支援
医療介護連携 :医師や看護師と連携した医療・介護サービス
生活相談 :入居者の日常生活に関する相談対応
リハビリテーション :身体機能の維持・向上を目的としたリハビリ
認知症ケア :認知症の専門知識を持つスタッフによる適切なケアと支援
これらのサービスは、入居者の自立を促しながら、認知症の進行を抑えて機能維持を図ることを目的としています。
ここに記載してあるものすべてがサビ管が行うものとは限りません。
あくまで生活支援員等の業務も合わせたものになります。
グループホームでは、入居者が可能な限り自分でできることは自分で行い、必要な部分で介助を受けながら生活することが基本となっています。
生活介護とグループホームの違い
生活介護とグループホームは似ているため、ここで違いについて解説していきます。
グループホームと生活保護は高齢者や障がいのある人に向けた支援を行っている点に関しては同じですが、厳密には異なる部分があります。
このように項目ごとで見てみると違いがハッキリ見えてきます。
一番の違いは、居住型か通所型かということです。
生活介護は施設に通うのに対してグループホームでは住んでいる場所で支援を受けることができます。
また、グループホームは比較的自立度の高い人を対象としているのに対し、生活介護はより重度の障害がある人を対象としています。
そのため、介護を中心に行うか支援を中心に行うかで存在目的がハッキリ分かれます。
グループホームで働くサビ管のメリット・デメリット

サビ管の働く場所として就労支援施設や通所系の事業所などがありますが、グループホームという施設の特徴に合わせてグループホームでサビ管として働くことについてメリット・デメリットの観点に分けて解説します。
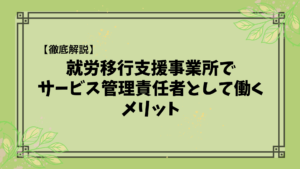
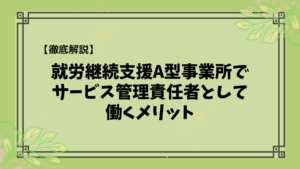
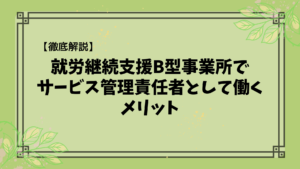
メリット
利用者さんと親しくなりやすい
グループホームは既存の建物を活用したり、都道府県知事が必要と認めない限りは基本的に10人以下で運営されます。
そのため、少人数に対して行う介護支援になるため親しくなりやすいです。
グループホームならではの特徴ですね。
対応力が身につく
サビ管は業務量が多いですが、その業務をこなしていくことで臨機応変に対応できる力が身に付きます。
また、日頃トラブルも多々発生するため問題解決力も身に付きます。
スタッフの成長も見ることができる
サビ管ならではのメリットではないでしょうか。
スタッフの人財育成もサビ管業務の一つとなるため利用者さんだけでなく、スタッフの支援員としての成長も見ることができます。
介護の知識・経験が活かせる
サビ管は看護師や世話人として勤務していた方が資格を取得するケースもあります。
対象となる相手は変わるものの業務内容としては似ているため経験したことを活かすことができます。
デメリット
メリットがある一方でいくつかのデメリットがあります。
勤務時間が長くなる可能性がある
グループホームは夜間の支援が基本的なため、夜勤業務が発生する場合があります。
基本的に勤務時間が16時間前後と長時間となることが多く、生活リズムが不規則になってしまうため、体力的にしんどいと感じる人が多くいます。
給料が働きに見合ってない
人の命を預かっているのにも関わらず、給料が低く見合ってないという声が多く見受けられます。
また、サビ管は管理者業務に加え生活支援員の業務を一部負担することもあります。そのため、業務量が多くきついと感じる人が多いようです。
精神的につらい
外部とのやり取りは基本的にサビ管が行います。
そのため、クレーム対応も外部とのやり取りの1つに入ります。これが精神的にしんどくなってしまう大きな原因であると考えられます。
※メリット・デメリットに分けてご紹介しましたが、人によって向き不向きが異なるためメリットがデメリットにデメリットがメリットに感じる方もいるかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はグループホームで働くサビ管のメリット・デメリットについて解説しました。
同じサビ管でも働く場所によって業務内容が変わってきます。
そのため、施設の特徴に合わせて適正をきちんと見極めることが大切です。
本記事が少しでも有益な情報となれば幸いです!
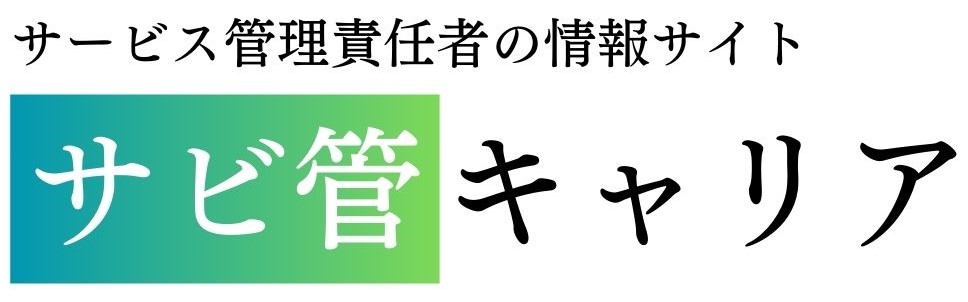
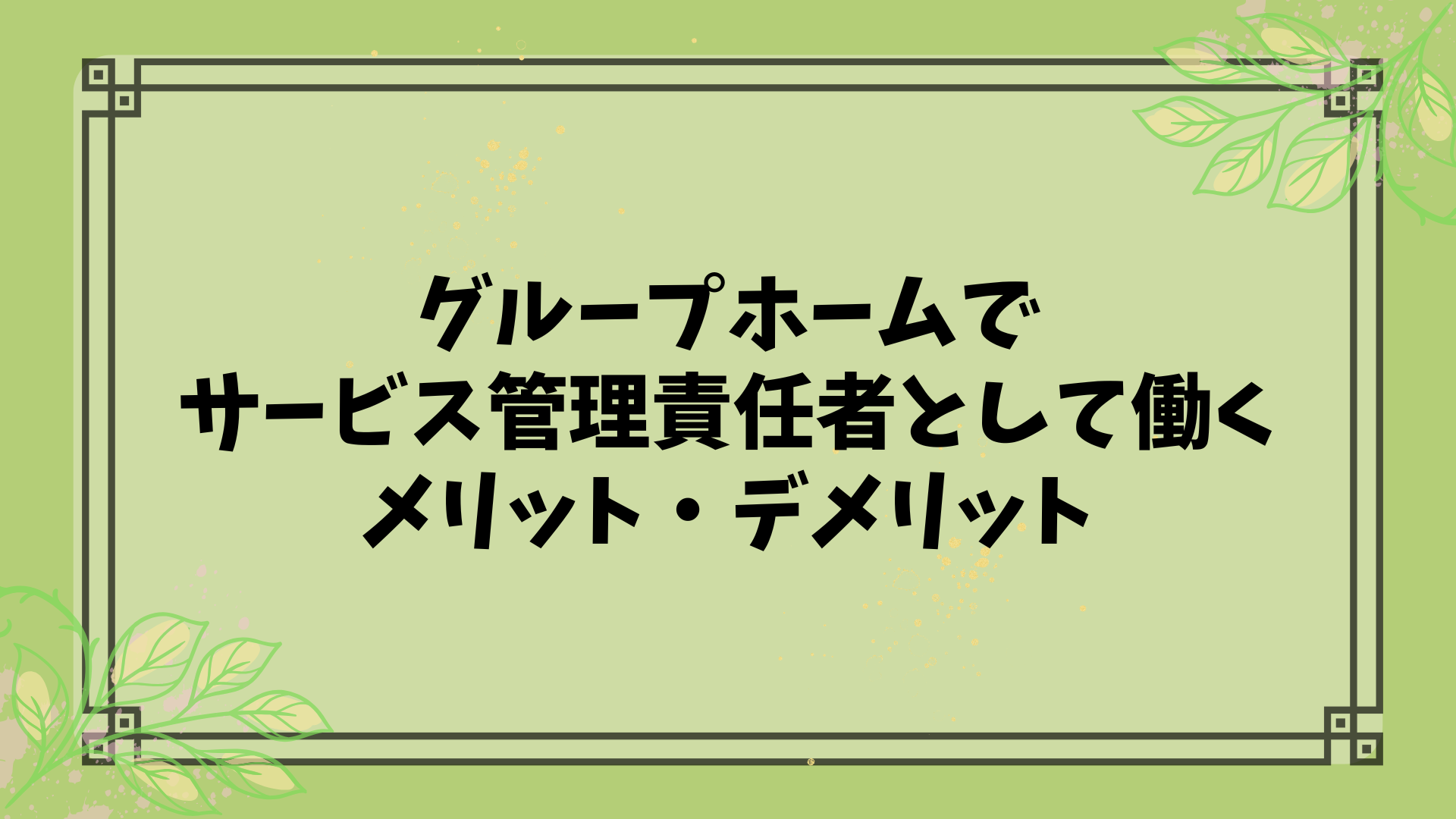
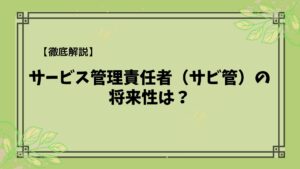
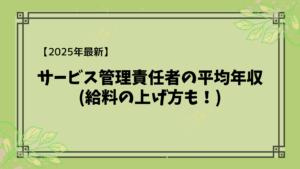
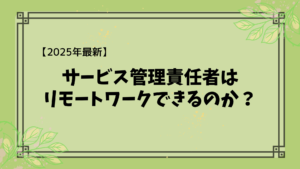
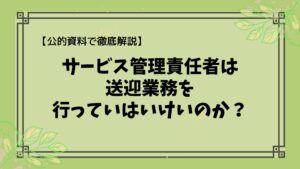
コメント